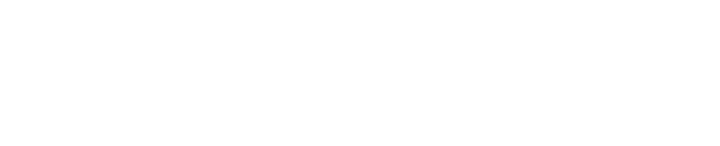金沢シンポジウム「能登からの発信」 レポート 2025.11.18
2025年10月5日(日)に、金沢シンポジウムを開催いたしました。財団理事、評議員より寄稿されましたレポートを掲載いたします。
上段左から: ロバート ジェンキンズ・大河原 恭祐 / 下段左から: 松原 創・坪木 和久 (敬称略)

総合討論の様子: 右端から司会の井田 徹治・坪木 和久・ロバート ジェンキンズ・大河原 恭祐 (敬称略)
【レポート1】矢島 道子(東京都立大学非常勤講師・財団理事)
今、緊急に開かなければならないナチュラルヒストリーのシンポジウムは何だろうと財団は考えた。2024年1月1日の能登半島地震で大きな被害を受け、同じ年の9月27日の豪雨でも甚大な被害を受けた能登半島の自然が今、どうなっているのか、どんな問題を抱えているのかを、シンポジウムで報告してもらうのがよいのではないかと考えた。
2025年10月5日午後1時から、金沢駅西口のTKPガーデンシティPREMIUMでシンポジウムを開催した。会議場には金沢の市民が、そして、関心を持っている全国の人々がオンラインで参じた。
まずは、地震に遭遇し、自宅の近くのマンホールが盛り上がっているのを目撃したロバート・ジェンキンズさんは、研究のメイン・フィールドである海そのものが今、どうなっているか調べて、「能登の海:地震・津波・豪雨で起きた海底の変化.そして生物は?」と報告した。実は、海の中の観測のほうが遠い宇宙よりずっと難しい。
人々は海の中のことを宇宙よりも知らない。海底にカメラを設置すると、あっという間に様々な生物に覆われてしまう。調べても調べてもなかなかわからない。それでも、能登からの要請で、全国の研究機関の観測船がやってきて、ボーリングも含めて、能登の海をかなり調査してくれた。地上の世界は早急に復興復旧の方向へ動くけれど、海の世界はいまだ混乱したままである。
能登半島は渡り鳥の通り道である。大河原恭祐さんは能登の渡り鳥を継続して研究していた。大地震と豪雨で何が変わっただろうか。渡り鳥の食べ物つまり果実の豊凶に変化が生じ、渡り鳥の集団、分布が変わるのだそうだ。そして、その渡り鳥の盛衰が植物群落の多様性に影響を及ぼしていくというように、能登の生態を変えているそうだ。つまり、渡り鳥を調査することで、地上の生態系の変化がわかるということだ。
松原創さんは金沢大学能登半島海洋生産センターで遭遇した地震・豪雨の出来事をまず報告した。センターは小規模ながら、地域の水産業への貢献を目指していた。いろいろな試みが完成しそうな時に、地震が襲った。水が止まって飼育していた魚たちが大量に死んだ。地震後の研究員たち自身の生活の保障も難しい中、奥能登の水産業復旧・復興を目指して、海洋生産センターの取り組みは続いた。研究員、関係者の工夫、機転、なんでも使う。本当によくぞ、ここまで復旧したものだと思う。しかしながら、水産業から見ると海洋の変化はまだ始まったばかりかもしれない。
最後の登壇者の、坪木和久さんは気象学者で、講演「激甚化する日本海側の豪雨と台風」は、豪雨と台風の実態とその影響を説いた。日本の近年の気候変化の激しさは世界中でもトップのレベルらしい。日本が一番甚大な変化を被っているということだ。今は、気象の変化がよく記録されているから、いわゆる線状降水帯はおこってから見直すと、そのメカニズムはよくわかる。ただし、実際に研究はどれだけ役に立っているかはまだまだのようだ。そして、台風は世界でもトップの大きな気象災害をもたらすから、日本が台風をよく研究しなければならないとして、その一例の台風の目玉の中に入る調査も紹介された。
最後のパネルディスカッションが素晴らしかった。講演者たちは、それぞれの講演時間を超え、力を込めて話されたが、他の講演者たちの講演に大きな影響を受けていたようだ。気候災害で、他分野の研究を知る機会はあまりないのかもしれない。たとえば、海洋の研究者が陸上の研究を具体的に知ることはあまりないかもしれない。ナチュラルヒストリーの醍醐味かもしれないが、パネルディスカッションではそれぞれがうまく融合して、発言力は、みな数倍になった。パネラーが他のパネラーに大いに学んでいる姿があった。会場の聴衆たちはもっと学ぶことができた。パネルディスカッションを4時間やってもよかったのではないかという声がでるくらいであった。
気候環境は絶望的にひどくなっている。自然環境も非常に厳しくなっている。たとえば、来夏はもっと暑くなるかもしれない。それを嘆くのではなく、絶望するのではなく、生物が長い地球時間を生きて、適応してきたように、私たちは、広い視野から自然を見て、どうするべきなのかを真摯に考えていくべきではないかと、パネルディスカッションは結んだ。
【レポート2】瀧澤 美奈子(科学ジャーナリスト・財団評議員)
激甚化する自然災害 より良い復興とは?~自然を見つめ続ける自然史からの発信~
2025年10月5日(日)、藤原ナチュラルヒストリー振興財団主催により「金沢シンポジウム『能登からの発信』」が石川県金沢市において開催された。2024年1月1日の能登半島地震と同年9月の豪雨災害を念頭に、地球生物学、生態学、水産学、気象学の研究者がそれぞれの視点から被害や復興状況、今後の見通しについて発表し、より良い復興や持続可能性のために、自然史がなしうることについて話し合った。
海底から陸地まで豊かな能登に刻まれた自然史
講演のトップバッターは、金沢大学 理工研究域 准教授のロバート・ジェンキンズさん。『能登の海: 地震・津波・豪雨で起きた海底の変化.そして生物は?』と題し、能登の海の豊かさと自然災害がもたらす影響を、地球生物学(Geobiology)の視点から自らの調査結果をもとに伝えた。
ロバートさんの研究グループは、地震発生直後の2024年1月から能登の海底調査を継続し、その変化を追跡記録している。能登の海は浅海から深海まで多様な環境をもつが、地震による海底地すべりで広範囲が泥に覆われたことが確認された。
たとえば半島北端の珠洲はケイソウ泥岩の産地で、この土を活かした陶芸の珠洲焼が有名だが、その沖の海底は、地震による土砂崩れで、どこもかしこもこの泥で覆われたという。さらに地震発生から半年あまり後に奥能登を襲った豪雨災害により、陸からの大量の土砂がその上を一面覆い、厚みは17センチにもなっているという。
一方、数メートル規模の顕著な隆起がみられた半島北西地域では、これまで海底下にあった海岸沿いが陸地となり、海岸生物が陸上に姿を現した。集落はこの隆起のおかげで津波に襲われずに済んだが、少し目線を南に移せば、有名な千枚田は地すべり地形の跡地であることを物語っており、まさに自然史が実感できる場所であると、写真と共に聴衆にわかりやすく示した。
「今やっている研究が何の役に立つのか、いつも自らに問いかけている。能登での知見や教育が、将来の南海トラフ地震や伊豆地震災害に役立てられたらいい」としめくくった。
〇能登の自然を守る渡り鳥、温暖化による懸念も
次に登壇したのは金沢大学 生命理工学類 准教授で野鳥の生態学が専門の大河原恭祐(きょうすけ)さん。『能登の渡り鳥と種子散布』と題して、渡り鳥に関する最近の自身の研究成果2つを紹介した。
なぜ渡り鳥の話かと思ったら、すぐに合点がいった。日本には春や秋に多くの渡り鳥が通過するが、日本海は重要なルートである。とくに日本海に面した能登半島から加賀平野にかけては、とりわけ大切な経由地や越冬地だという。ツグミ類やヒタキ類は、秋には果実を食べて排泄物とともに種子を撒き散らす。大河原さんの20年間の丹念な研究によれば、果実は豊作と凶作を一年ごとに繰り返すが、それを食べる野鳥は凶作時にはまんべんなく食べるため、結果として生態系を安定化させるように働いているという。
しかし、近年は気温上昇とともに樹木が減り、実をつけない草本植物が増えてきているという。鳥のほうは種の構成に変化はないが、飛来数が減ってきている。そのため、「今後さらに実をつける植物が減るのではないか」と懸念を示した。
もうひとつの研究でも、渡り鳥のオオヒシクイのような水鳥が湿性植物の種の多様性を保つ機能が確認された。「つまり、渡り鳥は能登の自然を守っているのです。復興のためにも、ぜひみなさんに豊かな能登の環境を見に来ていただきたいです」と述べた。
能登町と金沢大学が手を組み、地域発の水産資源を高度化
続いて『奥能登の水産業復旧・復興を目指した金沢大学能登海洋水産センターの取り組み』と題し、金沢大学理工学域 能登海洋水産センター センター長の松原 創(はじめ)さんが登壇した。
同センターは、金沢大学と能登町の「地域づくり連携協定」のもと、海洋生物資源の研究・教育拠点として2019年に開設された。以来、ノドグロ養殖技術やサヨリの完全養殖技術など、地域の水産資源を高度化する研究を行ってきた。ちなみに、サヨリは石川県産のサヨリということで「石川サヨリ」と名付けたとのことで、松原さんの明るい人柄とともに会場を和やかにした。
松原さんの講演では、能登半島地震と同年9月の豪雨災害の体験が克明に語られた。地震により、養殖水槽へ水が供給できなくなり、すべての魚が死んでしまったため廃棄した。しかしその水槽を生かして地域の方々にお風呂を提供したことや、トイレの下水管を自分たちで仮修復したことなど、大変な状況下でたくましく乗り越えてきた経験が、写真とともに印象強く伝わってきた。奧能登の推計人口は震災で12.4%減少したことも語られた。「これからも地域産業を支える役割を果たしていく」という力強い決意を感じた。
地球上最大の川、「大気の河」がもたらす甚大な豪雨災害
続く講演は『激甚化する日本海側の豪雨と台風』と気象学に関する話題。名古屋大学および横浜国立大学教授の坪木和久さんが登壇した。
坪木さんは気象学者の立場から、2024年9月の能登半島豪雨の原因となった線状降水帯の発生要因などについて解説した。この豪雨をコンピュータシミュレーションで再現したところ、朝鮮半島の西の海上にあった台風14号から日本海上の秋雨前線に向かって大量の水蒸気が流れ込み「大気の河」となって、能登半島付近に1時間あたり100ミリを超える雨を降らせる線状降水帯が発生したという。
日本付近の最近の雨は、年降水量は減少傾向なのに日最大雨量が増加している。つまり「極端な大雨」が増えている。昨年の能登豪雨のように、いくつかの原因が重なって「大気の河」ができると、それが上陸する場所で線状降水帯が発生する。大気の河は毎秒20万トンもの水を運んでおり、これはアマゾン川の2〜3倍に相当するという。私たちの頭上に、地球上最大の河は大気中に存在するという驚くべき事実である。大気の河の原因は地球温暖化。日本は世界平均の約2倍の速度で温暖化が進んでいる。今後も豪雨災害にさらに警戒が必要な所以だと訴えた。
坪木さんは航空機に乗り、直接スーパー台風の中に入って観測する研究手法でも知られる。講演中に観測時の動画が再生され、聴衆は迫力ある映像を食い入るように見つめた。「台風の航空機観測を2017年に始めたとき、試験飛行で能登半島から日本海上空を飛行し、地元の方々に大変お世話になりました。地震に続く豪雨災害で、現在も多くの皆様が災禍のなかにあることに心が痛みます。一日も早い復興をお祈りします」と述べた。
総合討論: 温暖化時代にこそ「自然観」の発信を
最後に総合討論が開かれた。ファシリテーターは同財団評議員で共同通信社 編集委員および論説委員の井田徹治さん。災害からの復興の際、次の災害に備えて発災前から準備をする方向性を示す言葉として、「より良い復興」(ビルド・バック・ベター: Build Back Better)という言葉があるが、能登の豊かな海や山の自然資産を生かしながら、これを実現するために必要なことは何か?という問いかけがなされた。
登壇者からは、さまざまな意見が出た。なかでもコロナ禍により世界的に経済活動が停滞したにもかかわらず、地球温暖化を止めることができなかった。今後もあきらめずに、気温上昇の幅を小さくする排出削減などの努力は必要だが、残念ながらこの温暖化が、少なく見積もっても一定程度は進むことを前提とした備えが必要であるという意見があった。
北陸では今後、さらに気温の上昇に伴い大気の湿潤化で積乱雲が発達し、集中豪雨と乾燥が起きやすくなり、フェーン現象が起きやすい地形的特徴から山火事のリスクも高まる。今後、ますます厳しい気象状況が到来し、その中で海や山の自然環境が変化していく。
それでも自然を守りながら共生するという「自然観」(自然に対する見方・考え方)を、いかに社会で広く共有できるか。そのためにも、能登のような自然にあふれた海や山で起きていることを一般の人々につぶさに発信し、社会のなかに豊かな自然観を醸成することが今後ますます重要になるという意見が出た。閉会後も聴衆と登壇者があちこちで輪になり、活発な意見を交わす光景がみられた。
東京都目黒区上目黒1丁目26番1号
中目黒アトラスタワー313
- TEL
- 03-3713-5635
当財団は、ナチュラルヒストリーの研究の振興に寄与することを目的に、1980年に設立され、2012年に公益財団法人に移行しました。財団の基金は故藤原基男氏が遺贈された浄財に基づいています。氏は生前、活発に企業活動を営みながら、自然界における生物の営みにも多大の関心をもち続け、ナチュラルヒストリーに関する学術研究の振興を通じて社会に貢献することを期待されました。設立以後の本財団は、一貫して、高等学校における実験を通じての学習を支援し、また、ナチュラルヒストリーの学術研究に助成を続けてきました。2024年3月までに、学術研究助成883件、高等学校への助成127件を実施しました。