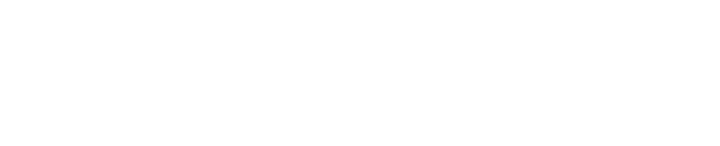シンポジウム: 記事一覧
シンポジウム
一般の方々並びに高校生をはじめとする若い人々のナチュラルヒストリーへ理解を深めるために、公開シンポジウムを開催しております。
第16回シンポジウム「新種発見の自然史」(ハイブリッド形式)感想 2024.12.03
藤原ナチュラルヒストリー振興財団第16回シンポジウムを、10月20日(日)に「新種発見の自然史」をテーマとして、会場(中央大学後楽園キャンパス)とオンラインのハイブリッドで開催した。
会場には一般の参加者のほか、中高生を含む学生、遠方からの参加者もみられた。今回、事務局のオンラインのURL送付ミスにより、オンライン参加者は少数となってしまった。楽しみにしておられた方には大変申し訳ありませんでした。今後は十分注意を払ってまいります。
テーマ「新種発見」について、次の4人の演者により講演がなされた。松浦啓一先生「魚の新種はどこからみつかるのか?新種発見の歴史と今後の展望」、田中伸幸先生「東南アジアの未知なる花-多様な新種発見・記載のプロセス」、奥村よほ子先生「新種発見は研究のはじまり」、宮脇律郎先生「鉱物の新種発見と国際鉱物学連合、新鉱物命名分類委員会の活動」。各講演後には参加者と講師による質疑応答が行われた。
「毎年楽しみにしている」「どの分野も興味深い」などのご感想等をいただいた。
今後も会場での参加のほか、全国からの参加が可能であるオンラインとのハイブリッド開催を検討したい。
第16回シンポジウム 開催のお知らせ【参加申込締切りました】 2024.07.25
当財団では、来る10月20日(日)に、藤原ナチュラルヒストリー振興財団第16回シンポジウム「新種発見の自然史」を、会場とオンライン配信のハイブリッドで開催いたします。事前申込制ですので、詳細をご確認のうえお申込み下さい。
なお、先着順に受け付けますので、お早めにお申し込み下さい。
九州シンポジウム「天変地異の時代〜火山列島に生きる〜」 レポート 2023.12.22
2023年10月15日(日)に、九州シンポジウムを開催いたしました。2名の財団理事等より寄稿されましたレポートを掲載いたします。
第15回シンポジウム「味の自然史」(ハイブリッド)感想 2023.11.24
藤原ナチュラルヒストリー振興財団第15回シンポジウムを、9月24日(日)に「味の自然史」をテーマとして、ハイブリッドで開催した。
参加者は、会場35名(中央大学 後楽園キャンパス)、オンラインでは68名の合計103名となった。一般の参加者のほか、中高生を含む学生の姿もみられた。
「味」について、次の4人の演者により講演がなされた。戸田安香先生「脊椎動物における旨味・甘味の進化史」、三坂巧先生「おいしさを決める「味覚」の不思議」、永田晋治先生「無脊椎動物・節足動物・昆虫が感じる味」、國府方吾郎先生「自然史から和食を考えてみよう-国立科学博物館の特別展「和食」を例に-」。各講演後には会場とオンライン参加者と講師による質疑応答が行われた。
「毎回楽しみにしている」「1つのテーマを多様な視点から聞くことができるので良い」などのご感想等をいただいた。
今後も会場での参加のほか、全国からの参加が可能であるオンラインとのハイブリッド開催を検討したい。
九州シンポジウム「天変地異の時代〜火山列島に生きる〜」(ハイブリッド)開催 2023.08.01
2023年10月15日(日)に、アクロス福岡において、九州シンポジウム「天変地異の時代〜火山列島に生きる〜」を開催いたします。
火山列島である日本、その火山の噴火の歴史や火山との共生、火山噴火予知などについ て研究することはナチュラルヒストリーそのものなのです。今回は「天変地異の時代〜 火山列島に生きる〜」と題して、第一線の火山科学者を講師に招き、最新の地球情報に ついて講演していただき、様々な観点からのパネルディスカッションもふくめたシンポ ジウムを開催します。皆様のご参加をお待ちしております 。
第15回シンポジウム 開催のお知らせ【 締切りました。】 2023.07.10
当財団では、来る9月24日(日)に、藤原ナチュラルヒストリー振興財団第15回シンポジウム「味の自然史」を、ハイブリッドで開催いたします。事前申込制ですので、詳細をご確認のうえお申込み下さい。
なお、先着順に受け付けますので、お早めにお申し込み下さい。
第14回シンポジウム「感染症の自然史」(オンライン)感想 2022.12.14 2022.12.14
藤原ナチュラルヒストリー振興財団第14回シンポジウムを、9月23日(金・祝日)に「感染症の自然史」をテーマとして、昨年に引き続きオンラインで開催した。
参加者は140名となり、東京及びその近県以外からも参加があり、高校生の参加が多くみられた。
「感染症」をテーマとして、4人の演者により、「感染症の自然史と衛生学」、「エイズの起源と歴史」、「遺伝子解析が語る結核菌と人類の歴史」、「ゆるやかな進化学が紐解くマラリアの薬剤耐性」と題した講演が行われた。また、各講演の後の質問時間の他にも、全講演終了後には総合討論を行い、さらなる質問に対しては講師からオンライン上のQ&Aで回答された。
残念ながら昨年に続き今年度も、聴衆と講師とのシンポジウム後の歓談や質問の姿を見ることはできなかったが、「とても勉強になりました」「自分の送った質問を回答してもらっているのが嬉しかった」などのご感想等をいただいた。
次年度以降の状況は不明であるが、全国からの参加が可能であるオンライン開催を望む声も多く、シンポジウムの開催方法等を検討していきたい。
第14回シンポジウム オンライン開催のお知らせ【参加申込が定員に達したため、締切りました。】 2022.07.29
当財団では、来る9月23日(金・祝)に、藤原ナチュラルヒストリー振興財団第14回シンポジウム「感染症の自然史」を、オンラインで開催いたします。事前申込制となりますので、以下の詳細をご確認のうえ、お申込み下さい。
先着順に受け付けますので、お早めにお申し込み下さい。
※ 毎年同日開催しております「高校生ポスター研究発表」は、新型コロナウィルスの感染防止のために、本年は11月13日(日)にオンライン開催とします。当財団Webサイトの高校生ポスター研究発表のタグから、詳細をご覧ください。
第13回シンポジウム「川の自然史」(オンライン)感想 2021.12.21
藤原ナチュラルヒストリー振興財団第13回シンポジウムを、11月28日(日)に「川の自然史」をテーマとして、昨年に引き続きオンラインで開催した。
参加者は128名となり、東京及びその近県以外からの参加のほか、11月14日に開催した高校生ポスター研究発表に参加された高校生の他、それ以外の高校生の参加もみられた。
「川」をテーマとして、4人の演者による、地質、動物、植物、また展示(川を見る視点)に関しての講演が行われた。各講演の後の質問時間の他にも、全講演終了後には総合討論を行い、さらなる質問に対しては講師からオンライン上のQ&Aで回答された。
残念ながら、今年も例年のような聴衆と講師とのシンポジウム後の歓談や質問の姿を見ることはできなかったが、聴衆より「日本の生態の多様性の理由の一端がわかった気がする」「川や地質は奥が深そうなので、更に詳しく勉強して見たいと思う」というご感想等をいただいた。また、高校生ポスター研究発表の表彰もあったことから「支援を通じて羽ばたいた高校生たちの現在の様子も知りたい」等のコメントもいただいた。
次年度以降の状況が不明であるが、全国からの参加が可能であるオンラインでを望む声も多く、今後のシンポジウムの開催方法等を検討していきたい。
東京都目黒区上目黒1丁目26番1号
中目黒アトラスタワー313
- TEL
- 03-3713-5635
当財団は、ナチュラルヒストリーの研究の振興に寄与することを目的に、1980年に設立され、2012年に公益財団法人に移行しました。財団の基金は故藤原基男氏が遺贈された浄財に基づいています。氏は生前、活発に企業活動を営みながら、自然界における生物の営みにも多大の関心をもち続け、ナチュラルヒストリーに関する学術研究の振興を通じて社会に貢献することを期待されました。設立以後の本財団は、一貫して、高等学校における実験を通じての学習を支援し、また、ナチュラルヒストリーの学術研究に助成を続けてきました。2024年3月までに、学術研究助成883件、高等学校への助成127件を実施しました。